AppleとMetaに7億ユーロ(約1,000億円)の罰金!EUのデジタル市場法(DMA)は米国企業いじめ?その背景を探る
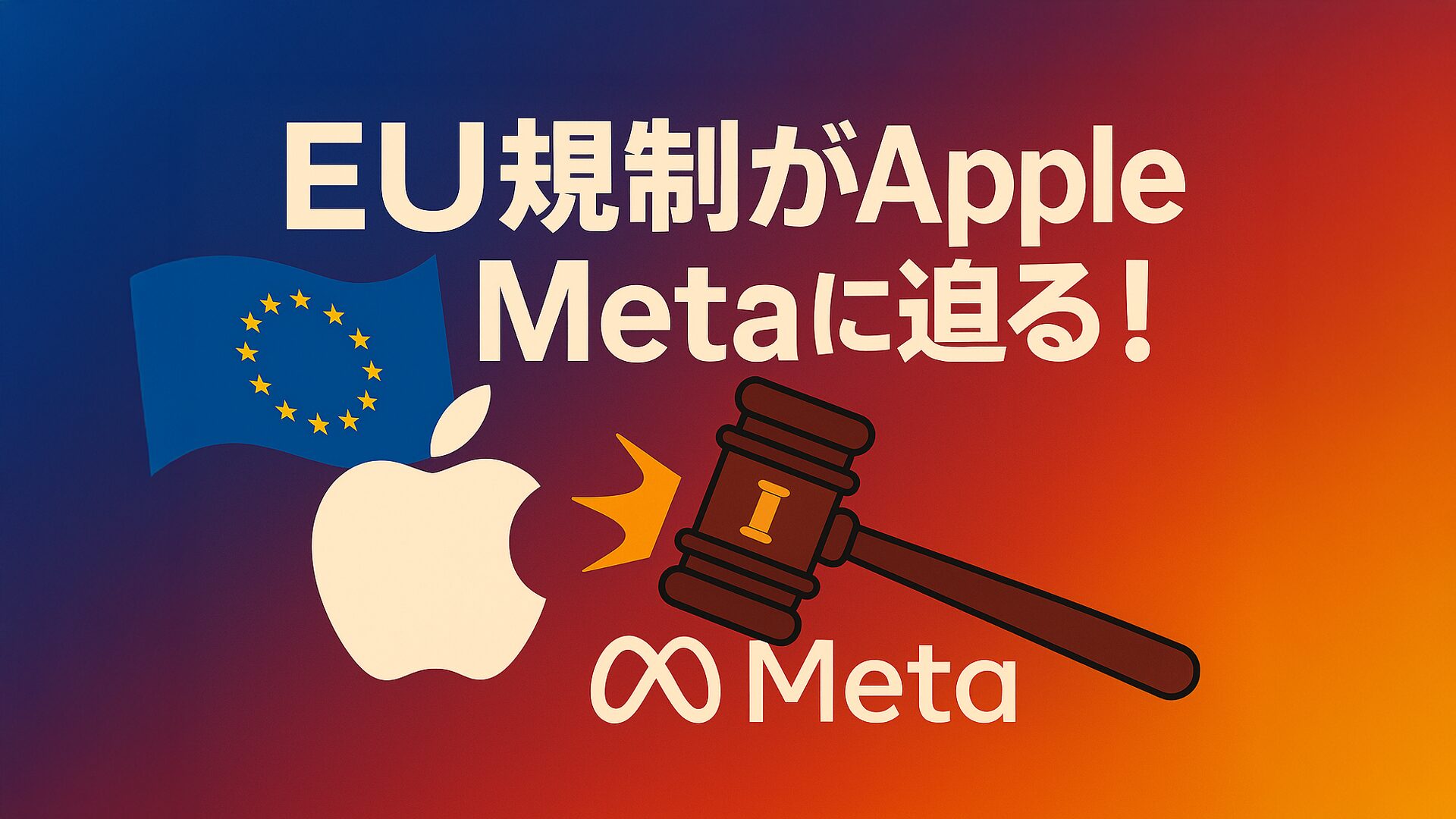
欧州連合(EU)が、私たちがよく知っているテクノロジー大手のAppleとMetaに対して、合計で7億ユーロ(約1,100億円)という大きな罰金を科したのです。いったい何があったのでしょうか?。
そもそもEUって何?なぜ大企業に罰金を科せるの?
欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会(EC)が、巨大IT企業のAppleとMeta(FacebookやInstagramの親会社ですね)に対して、合計で7億ユーロ(日本円にして約1,100億円以上!)もの巨額な罰金を科したのです。なんでも、「デジタル市場法(DMA)」っていう新しいルールに違反した、というのが理由だそうです。
EU側は「競争を守るためだ!」と主張していますが、なんだか腑に落ちない点もあるんですよね。そもそもEUって、ヨーロッパの国々が一つになって世界と競争するために作られたはず。
でも、そのために各国の主権や文化を犠牲にして、大きくて動きの鈍い官僚組織を作ってしまったんじゃないか、なんて声も聞こえてきます。そして、結局EUが主導権を握っても、本当に世界と渡り合える競争力がついたのか…? 今回の罰金騒動も、そんなEUの現状を映し出しているのかもしれません。
Appleはどんなルール違反をしたの?
Appleは「App Store」というアプリを配布する場所を持っています。EUによると、Appleはアプリの開発者たちに対して、「App Store以外の場所で同じアプリをもっと安く売っていることをユーザーに教えちゃダメ」というルールを設けていたそうです。
欧州委員会は「開発者は無料で、App Store以外での提供についてユーザーに知らせ、そちらに誘導し、購入できるようにすべきだ」と言っています。でも、Appleがいろいろな制限を設けているせいで、開発者たちはApp Store以外の販売方法のメリットを十分に活かせず、ユーザーも安いオファーの恩恵を受けられないんだとか。
そのため、EUはAppleに5億ユーロ(約800億円)という大きな罰金を科したのです。
Metaの問題点は?
一方、MetaはFacebookやInstagramを運営している会社ですね。EUのルールでは、Metaはユーザーの個人データをどう使うかについて、ちゃんと同意を得なければいけません。
2023年11月から、MetaはEUのユーザーに「個人データを組み合わせて広告に使うことに同意するか、それとも月額料金を払って広告なしのサービスを使うか」という選択を提示していました。でも、EUはこれをDMAに違反していると判断したのです。
なぜなら、この選択肢は「個人データを少なく使うけど同等の無料サービス」という選択肢を提供していなかったからです。つまり、「広告付きで個人情報をたくさん使われる」か「お金を払う」かの二択しかなく、「広告付きでも個人情報をあまり使われない」という選択肢がなかったのです。
そのため、MetaにはEUから2億ユーロ(約320億円)の罰金が科されることになりました。
両社の反応は?
もちろん、AppleもMetaも、この罰金決定には納得していません。
Metaは「EUはパーソナライズド広告を不当に制限している」と主張。「ビジネスモデルを変えろというのは、事実上何十億ドルもの関税をMetaに押し付けることになる」と不満を述べています。また、「EUは米国の成功企業を不当に攻撃している」とも言っています。
Appleも「ユーザーのプライバシーとセキュリティに悪影響を与え、製品にも悪影響が出る」と批判。「このルールに従うために何百万時間もエンジニアリングの時間を費やし、何十もの変更を行ったが、ユーザーは誰も望んでいない」とも述べています。
なぜ罰金は「控えめ」?EUの複雑な事情とは
ところで、AppleとMetaの年間売上高を考えると、今回の5億ユーロや2億ユーロという罰金額は、実はそれほど大きくない、とも言われています。DMAでは、違反企業に対して、全世界の年間売上高の最大10%もの罰金を科すことができると定められています。AppleやMetaの規模からすれば、本来なら何十億ユーロ、場合によっては兆円単位の罰金もあり得たわけです。
では、なぜ今回は比較的「控えめ」な金額になったのでしょうか?ロイター通信の報道によると、いくつかの理由が考えられるようです。
- 違反期間の短さ: DMAの義務が発効してから違反が認定されるまでの期間が比較的短かったこと。
- コンプライアンス重視: EUが制裁そのものよりも、企業にルールを守らせること(コンプライアンス)を重視している姿勢を示したかったこと。
- 政治的な配慮?: 米国のトランプ大統領(からの報復措置を避けたい、という政治的な思惑があった可能性。
特に3つ目の理由は興味深いですね。EUの決定が、純粋な法律論だけでなく、国際的な政治状況にも影響されている可能性を示唆しています。巨大な官僚組織であるEUが、必ずしも一貫した論理だけで動いているわけではない、ということなのかもしれません。なんだか、自分たちの都合でルールを運用しているような印象も受けてしまいます。
EUは本当に「競争」できるのか?規制強化の先にあるもの
さて、今回のAppleとMetaへの罰金騒動を見てきて、冒頭で触れた個人的な疑問が、やはり頭をもたげてきます。
EUはヨーロッパの競争力を高めるために作られたはずなのに、やっていることと言えば、巨大な官僚組織を動かして、外国の成功企業に次々とルールを課し、罰金を科すことばかりに見えてしまうのです。
もちろん、巨大企業の力を抑制し、公正な競争環境を作ることは重要です。しかし、EUのやり方は、時に非効率で、不透明で、そして特定の企業に対する敵意のようなものさえ感じさせます。
新しい法律(DMA)を作っても、その運用がコロコロ変わったり、政治的な配慮が見え隠れしたりするようでは、企業は安心してビジネスを展開できません。
Appleが言うように、「ユーザーが誰も求めていない変更」を強いられ、膨大な時間とコストを費やさなければならないとしたら、それはイノベーションの妨げにしかならないのではないでしょうか。
Metaが指摘するように、米国企業ばかりが厳しい基準を課され、他の地域の企業が見逃されているとしたら、それは公正な競争とは言えません。
EUは、自らが掲げる「競争力強化」という目標を、本当に達成できるのでしょうか?
巨大テック企業を締め付けることで、かえってヨーロッパ全体のデジタル経済の活力を削いでしまう結果にならないでしょうか? 非民主的で官僚的な組織が、本当に未来を切り開くイノベーションを生み出す土壌となり得るのか、私には疑問に思えてなりません。
国家主権や独自の文化を犠牲にしてまで作り上げた巨大組織が、結局は世界との競争に勝てないどころか、足を引っ張っているだけだとしたら、それはあまりにも皮肉な結果ではないでしょうか。
日本のユーザーへの影響
2024年6月に成立した「スマホソフトウェア競争促進法」、ひと言でいえば、AppleとGoogleという「スマホ界の巨人」の力を少し抑えて、もっと他の会社も競争に参加しやすくしよう!というものです。EUのDMAと考え方はとても似ていますね。
先月(2025年3月)、予定通り公正取引委員会がApple(具体的にはApple自身とiTunes)とGoogleを「指定事業者」にバシッと指定しました。これは、「あなたたちの影響力は特に大きいから、この新しいルールの対象ですよ」という宣言みたいなものです。そして、今年の12月までには、この法律が全面的に動き出すことになっています。
期待と不安
この法律によって、日本のスマホ市場やアプリ開発業界が活性化する、という期待の声があります。国内の企業が新しいアプリストア事業に参入したり、開発者がより自由な発想でアプリを作れるようになったりするかもしれません。
でも、個人的には、EUのDMAの時と同じような疑問も感じています。
- 本当に「競争」は健全に進むのか?: ルールを変えるだけで、本当にAppleやGoogleに対抗できるような新しいプレイヤーが育つのでしょうか?
- セキュリティリスクへの対応は万全か?: 便利さや安さと引き換えに、ユーザーが危険に晒されるような事態は避けなければなりません。国(公正取引委員会)は、しっかり監視できるのでしょうか?
- 官僚主導でイノベーションは生まれる?: 結局、役所がルールを決めて企業を縛るというやり方で、本当に新しい技術やサービスが生まれやすくなるのか、少し懐疑的です。EUと同じ轍を踏まないか、心配な部分もあります。
- AppleやGoogleとの関係: Appleは「ユーザー体験の低下を懸念する」と言いつつ、日本政府と協議を続けているようです。EUと同様、法律の施行後も、解釈や運用をめぐって様々な駆け引きが続くのかもしれません。
まとめ
EUはDMA(デジタル市場法)を根拠に、AppleとMetaに合計7億ユーロの罰金を科した。
AppleはApp Storeでの情報提供制限(アンチステアリング)、Metaは個人データ利用の同意モデル(Consent or Pay)が問題視されました。
両社ともEUの決定に強く反発しており、特にMetaは「米国企業いじめだ」と主張しています。
罰金額が比較的小さかった背景には、政治的な配慮もあった可能性が指摘されています。
個人的には、EUの規制強化が本当に競争力向上につながるのか、官僚主義的な組織運営に疑問を感じます。
EUと巨大テック企業の対立は、まだ始まったばかりです。DMAに基づく調査は他の企業に対しても進められており、今後も同様のケースが出てくる可能性があります。
AppleもMetaも、今回の決定に対して不服を申し立てる姿勢を見せており、法廷闘争に発展するかもしれません。
この対立が、私たちの使うサービスや、インターネット全体の未来にどのような影響を与えるのか、注意深く見守っていく必要がありそうです。
そして、EUのやり方が本当に正しいのか、私たち自身も考えていく必要があるのではないでしょうか。


LEAVE A REPLY