複数Mac環境でObsidianとGemini CLIを完全連携!TerminalとShell Commandプラグインで実現する効率的なAI執筆環境
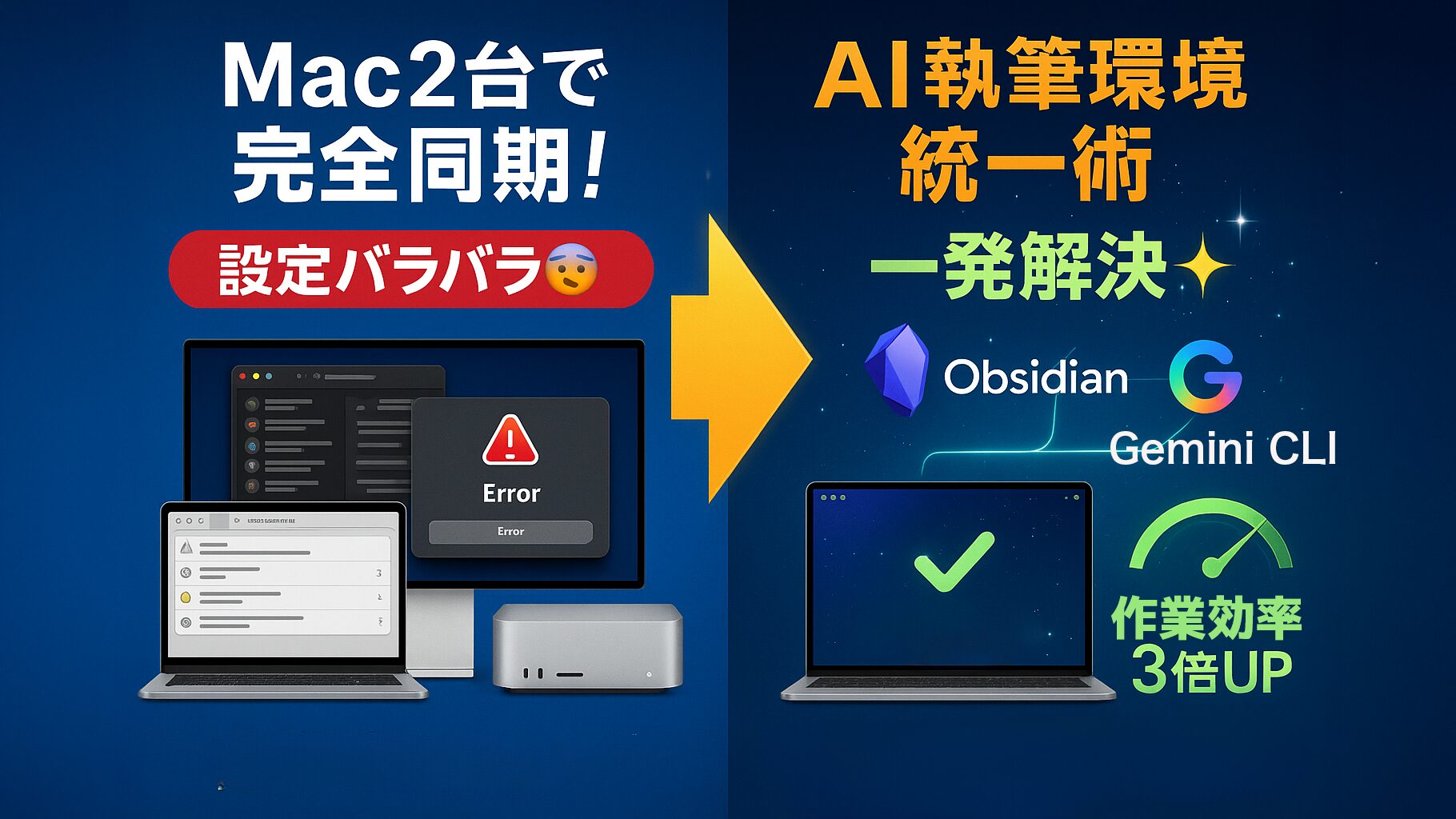
デスクトップとMacBook Proを使い分けながらObsidianで執筆していると、「どちらのMacでも同じようにAIを活用したい」と思いませんか?
私も同じ悩みを抱えていました。特に、2台のMacでログイン名が異なる環境では、設定が非常にややこしくなってしまいます。しかし、試行錯誤の末、ObsidianのコミュニティプラグインとGemini CLIを組み合わせることで、どちらのMacでもスムーズにAIを活用できる環境を構築できました。
この記事を読み終える頃には、あなたも複数のMac環境で統一されたAI執筆環境を手に入れ、執筆効率が大幅に向上することでしょう。
前提条件と参考リソース
この記事では、Gemini CLIのインストールと基本設定は完了している前提で進めます。まだインストールしていない方は、以下の優れた記事を参考にしてください。
初心者向けリソース
- 【初心者向け】WindowsでGemini CLIを使ってみよう!(Windows環境ですが、手順は参考になります)
- Gemini CLI の簡単チュートリアル – Zenn
技術的な詳細を知りたい方向け
トラブルシューティング
- Gemini CLIの初期設定!超簡単!…と思いきや大苦戦?(Google Workspaceユーザー必見)
なぜObsidianとGemini CLIの連携が必要なのか
Obsidianで長文を書いていると、こんな場面に遭遇することがあります。
- 書いた文章を要約してほしい
- アイデアをもっと広げたい
- 文章の表現を改善したい
- 関連する情報を調べたい
これらの作業で、いちいちブラウザを開いてGeminiにコピペするのは面倒ですよね。ObsidianからダイレクトにGemini CLIを呼び出せれば、思考の流れを止めることなく、AIの力を借りることができます。
iCloud Driveを使った複数デバイス同期について
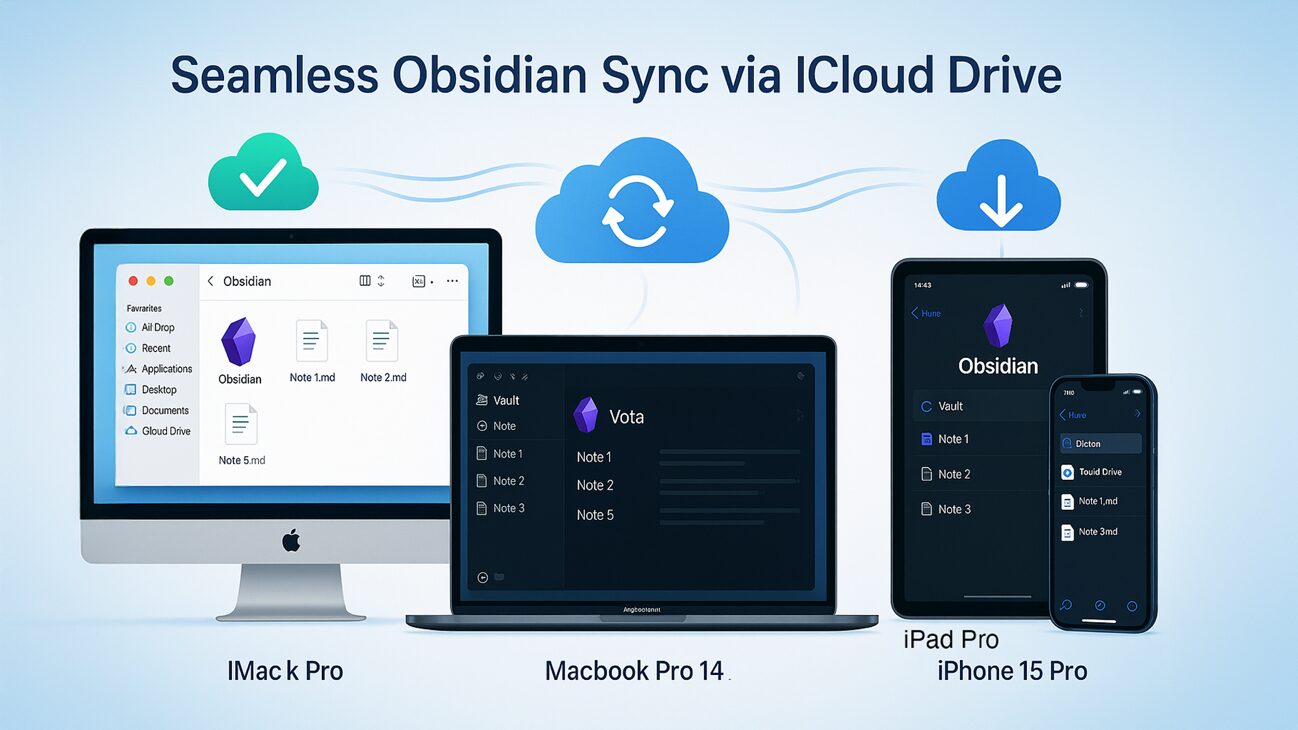
私のような以前からのObsidianユーザーは、Obsidian Syncサービスが存在しなかった時代から、複数デバイスでの執筆環境を構築する必要がありました。
そこで多くのユーザーが採用したのが、iCloud DriveにVault(保管庫)を置くという方法です。これにより、デスクトップMac、MacBook Pro、iPad、iPhoneといったすべてのAppleデバイスから同じノートにアクセスできるようになりました。
「iCloud Driveは同期が遅い」という声を聞くこともありますが、私の経験では全く不便を感じたことがありません。例えば、移動中にiPadで記事の下書きを書いて、帰宅後にMacでObsidianを起動すると、すでに内容が反映されています。この即座の同期により、デバイスを意識することなく、いつでもどこでも執筆を続けることができるのです。
このiCloud Drive環境があるからこそ、今回紹介する複数Mac環境でのGemini CLI連携設定が重要になってくるのです。
必要なプラグインのインストール
まず、Obsidianのコミュニティプラグインから以下の2つをインストールします。
1. Terminalプラグイン
Obsidian内でターミナルを直接開けるようにするプラグインです。設定画面から「コミュニティプラグイン」を開き、「Terminal」で検索してインストールします。
2. Shell Commandプラグイン
カスタムコマンドを登録し、ショートカットキーで実行できるようにするプラグインです。同様に「Shell Commands」で検索してインストールします。
複数Mac環境での最大の難関:ログイン名の違い
ここが今回の記事の核心部分です。私の場合、デスクトップMacとMacBook Proでログイン名が異なっていたため、設定に非常に手間取りました。
例えば、デスクトップでは「desktop-user」、MacBook Proでは「laptop-user」というログイン名だった場合、Obsidianの保存場所へのパスが異なってしまいます。
デスクトップ: /Users/desktop-user/Library/Mobile Documents/... MacBook Pro: /Users/laptop-user/Library/Mobile Documents/...
この問題を解決するために、
$(whoami)
というコマンドを使用しました。これは現在ログインしているユーザー名を自動的に取得してくれる便利なコマンドです。
Terminalプラグインの設定:統一プロファイルの作成
ステップ1:新規プロファイルの作成
Terminalプラグインの設定画面を開き、「Profiles」セクションで新規プロファイルを作成します。私は「Obsidian_Gemini」という名前にしました。
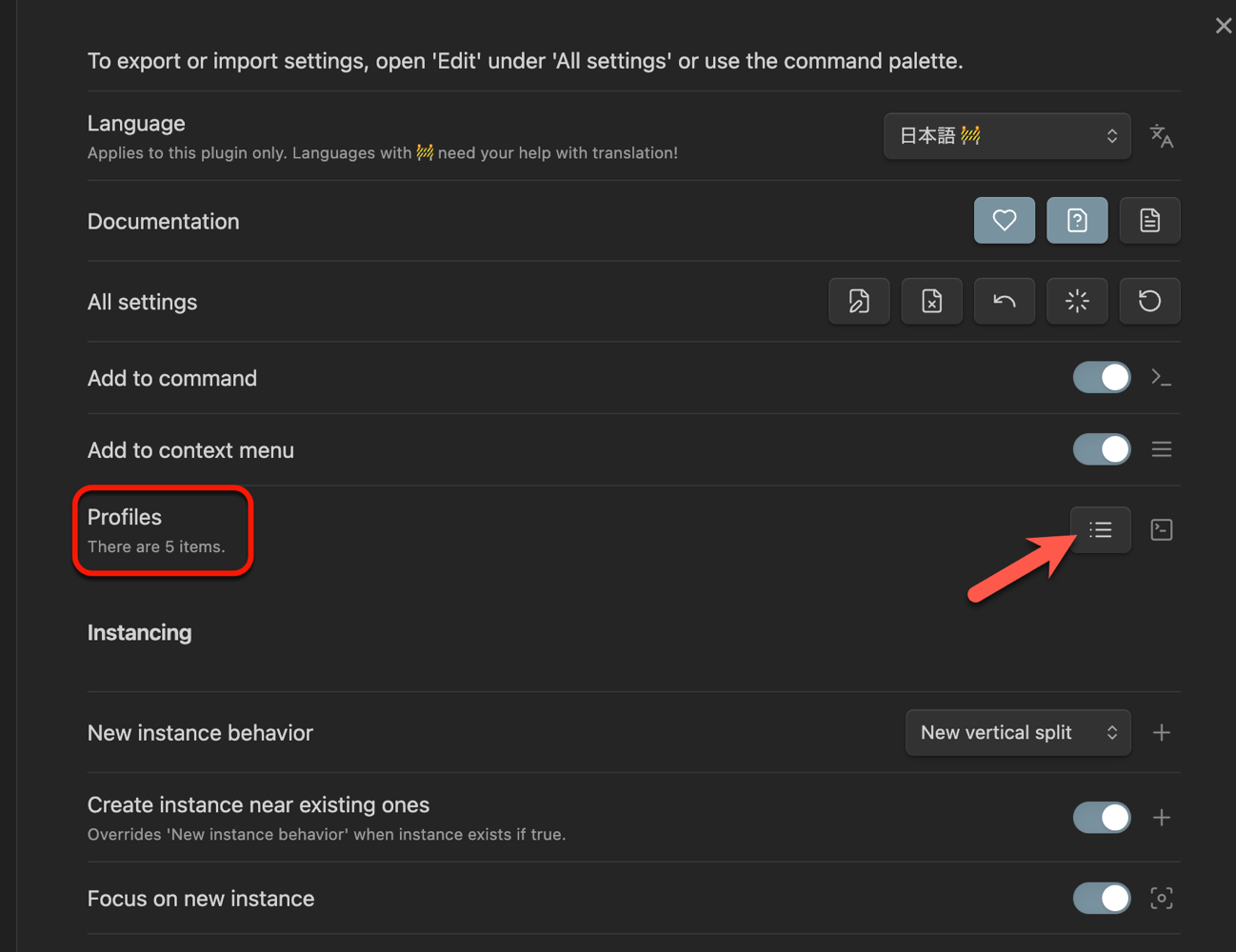
ステップ2:Argumentsの設定
ここが最も重要な部分です。以下の設定を行います:
1つ目の引数:
-c
2つ目の引数:
export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH" && cd "/Users/$(whoami)/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/Obsidian" && exec zsh
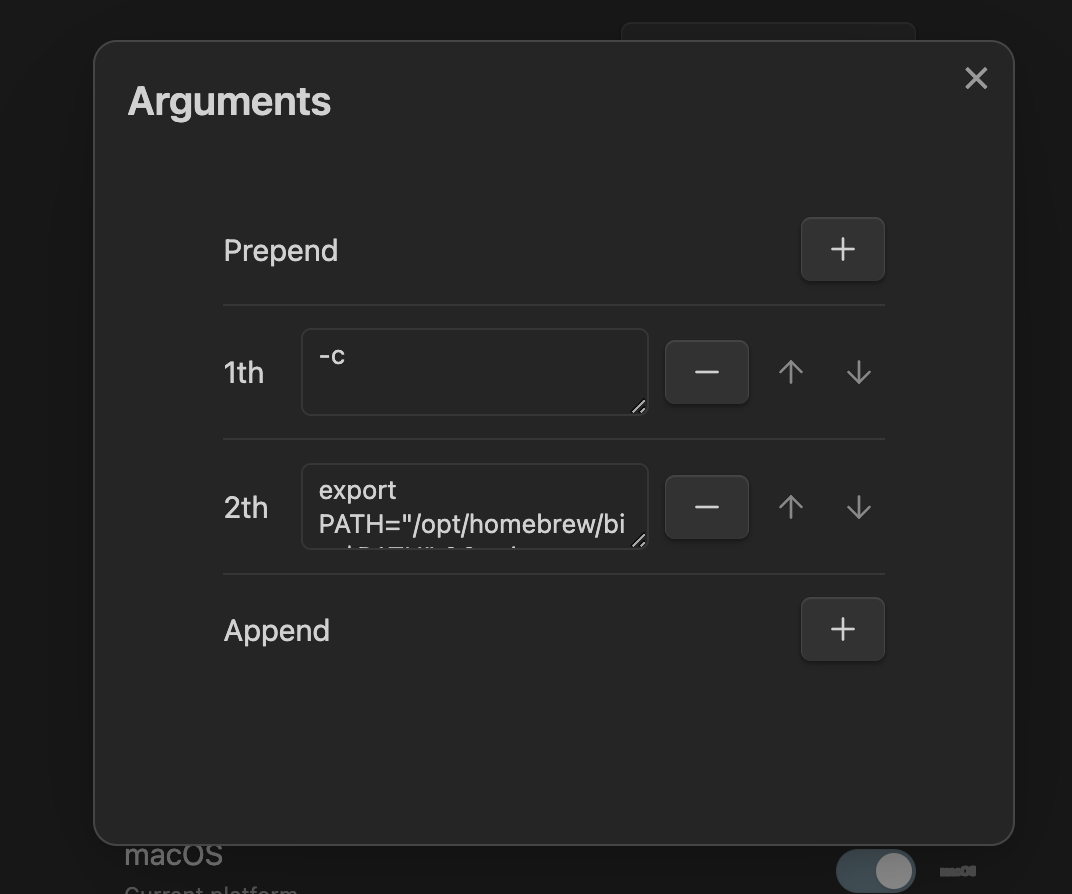
この設定の意味を分解して説明します:
- HomebrewでインストールしたGemini CLIへのパスを通します
- 現在のユーザー名を自動取得してObsidianのディレクトリに移動します
- zshシェルを起動します
export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH"
cd "/Users/$(whoami)/Library/Mobile Documents/..."
exec zsh
この設定により、どちらのMacでも同じプロファイルを使用できるようになりました。
Shell Commandプラグインでの自動化設定
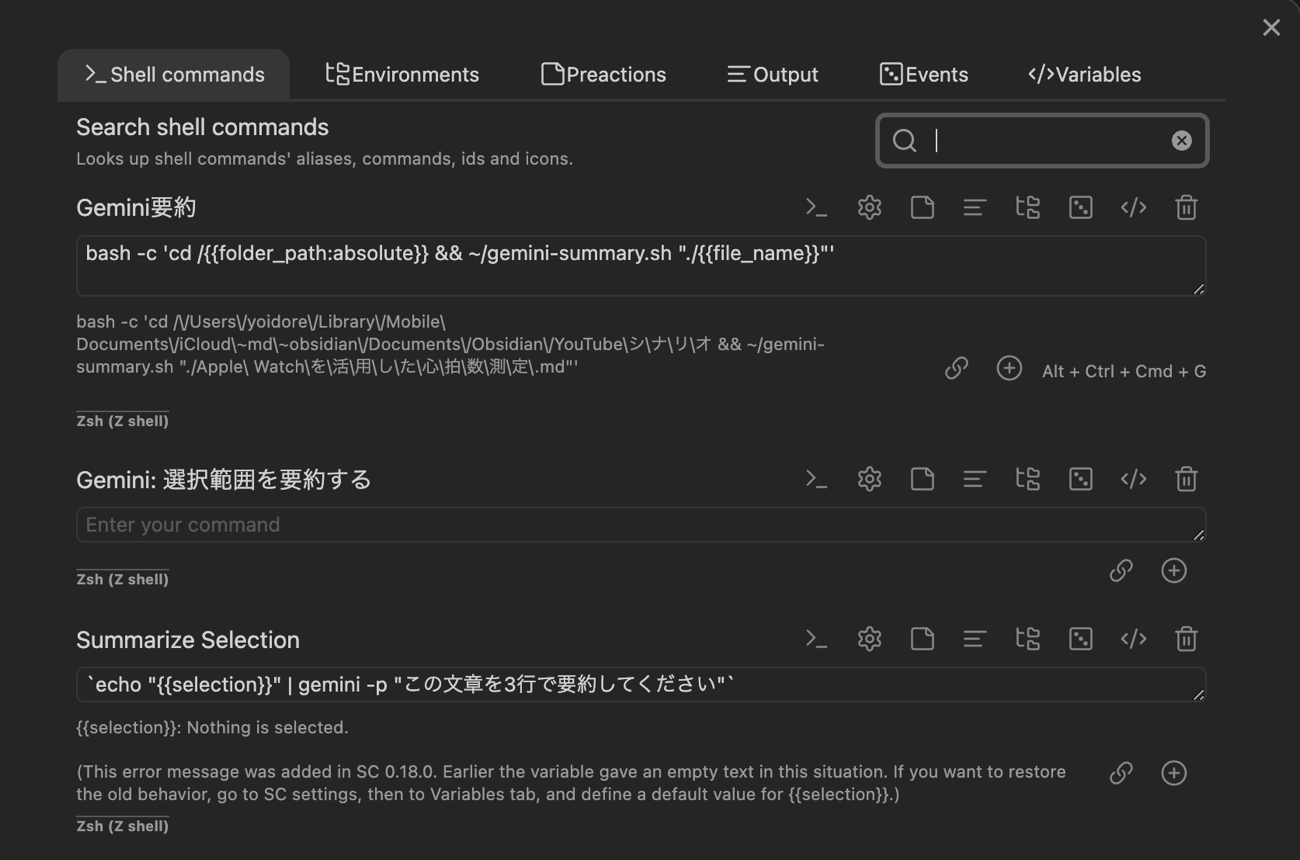
Terminalプラグインで基本的な環境は整いましたが、さらに便利にするためにShell Commandプラグインを活用します。
よく使うコマンドの登録例
1. 選択テキストの要約
コマンド名: Summarize Selection
コマンド:
echo "{{selection}}" | gemini -p "この文章を3行で要約してください"
ショートカット: Cmd+Shift+S
2. アイデアの展開
コマンド名: Expand Idea
コマンド:
echo "{{selection}}" | gemini -p "このアイデアをさらに5つの観点から展開してください"
ショートカット: Cmd+Shift+E
3. 文章の改善提案
コマンド名: Improve Writing
コマンド:
echo "{{selection}}" | gemini -p "この文章をより分かりやすく、自然な日本語に改善してください"
ショートカット: Cmd+Shift+I
出力結果の処理
Shell Commandプラグインでは、コマンドの実行結果をどのように扱うかも設定できます。私のおすすめ設定は:
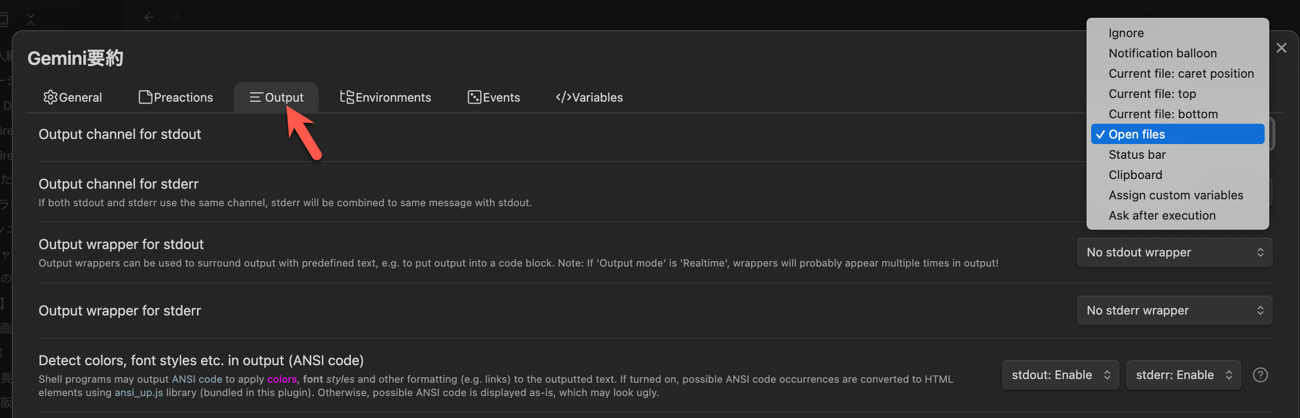
- Ignore;無視
- Notification balloon;通知バルーン
- Current file: caret position;現在のファイル:カーソル位置
- Current file: top;現在のファイル:先頭
- Current file: bottom;現在のファイル:末尾
- Open files;開いているファイル
- Status bar;ステータスバー
- Clipboard;クリップボード
- Assign custom variables;カスタム変数を割り当てる
- Ask after execution;実行後に確認する
これにより、結果を確認してから必要な部分だけをノートに貼り付けることができます。
実践的な活用シナリオ
朝の振り返りノート作成
毎朝、前日の作業内容を振り返るノートを作成しています。箇条書きで書いた内容を選択して、以下のコマンドを実行:
echo "{{selection}}" | gemini -p "この作業内容から、今日優先すべきタスクを3つ提案してください"
ブログ記事の構成作成
記事のアイデアをざっくり書いた後、それを選択して:
echo "{{selection}}" | gemini -p "このアイデアを元に、ブログ記事の見出し構成を作成してください"
技術メモの整理
散らかった技術メモを選択して:
echo "{{selection}}" | gemini -p "この技術メモを体系的に整理し、見出しをつけて構造化してください
トラブルシューティング
Gemini CLIが見つからないエラー
もし「command not found: gemini」というエラーが出た場合、PATHの設定を確認してください。M1/M2 Macの場合、Homebrewのパスが
/opt/homebrew/bin
になっていることが多いです。
日本語が文字化けする
ターミナルの文字コード設定を確認してください。Terminalプラグインの設定で、エンコーディングを「UTF-8」に設定すると解決することが多いです。
iCloud同期の遅延
複数デバイス間でObsidianを同期している場合、iCloudの同期遅延により最新のファイルが反映されないことがあります。重要な作業の前には、同期が完了していることを確認しましょう。
パフォーマンスの最適化
メモリ使用量の削減
Gemini CLIを頻繁に呼び出すと、メモリ使用量が増加することがあります。定期的にターミナルセッションを再起動することで、メモリを解放できます。
レスポンス速度の改善
長文を処理する場合、レスポンスに時間がかかることがあります。文章を適切な長さ(500〜1000文字程度)に分割して処理すると、より快適に使用できます。
さらなる活用のアイデア
テンプレートとの組み合わせ
Obsidianのテンプレート機能と組み合わせることで、さらに効率化できます。例えば、議事録テンプレートに「AI要約欄」を設けておき、会議後にワンクリックで要約を生成できます。
Daily Notesとの連携
Daily Notesプラグインと組み合わせて、毎日の振り返りを自動化することも可能です。その日のノートを丸ごとGemini CLIに渡して、重要なポイントを抽出してもらうことができます。
プラグイン連携の可能性
DataviewプラグインやTemplaterプラグインと組み合わせることで、より高度な自動化も実現できます。例えば、特定のタグがついたノートを自動的に収集し、それらを基にレポートを生成するといったワークフローも構築可能です。
まとめ:AI時代の新しい執筆スタイル
ObsidianとGemini CLIを連携させることで、思考と執筆のプロセスが劇的に変化しました。アイデアが浮かんだらすぐにAIに相談でき、文章の推敲も瞬時に行えるようになりました。
特に複数のMac環境で作業する私にとって、
$(whoami)
を使った統一設定の発見は大きなブレークスルーでした。この設定により、どちらのMacでも同じワークフローで作業できるようになり、生産性が大幅に向上しました。
AIツールは使い方次第で、単なる便利ツールから、思考のパートナーへと進化します。ぜひこの記事を参考に、あなたなりのAI執筆環境を構築してみてください。
きっと、執筆がもっと楽しく、もっと効率的になるはずです。


LEAVE A REPLY